社会貢献で節税も?寄付金の扱いと注意点― 制度の正確な理解が、適切な経費化と税務リスク回避につながる ―
1.導入:社会貢献への関心の高まりと“寄付金”の落とし穴
近年、企業による社会貢献活動が注目され、NPOへの寄付や災害支援、地域活動への協賛など、寄付金を支出する機会が増えています。
しかし一方で、「良いことをしたから経費になるはず」「寄付金は全部落とせる」といった誤解も少なくありません。
寄付金には、法人税法上の厳密な区分があり、その扱いに誤りがあると、税務調査で否認される可能性があります。
適切な判断のためには制度の理解が不可欠です。本稿では、寄付金の種類・限度額・注意点を整理し、実務で迷わないための基礎知識を解説します。
2.制度解説:寄付金の基礎と法人税法上のルール
(※2025年時点の法令に基づく)
法人税法では寄付金を次の3区分に分類しています。
●① 国や地方公共団体への寄付金
全額損金算入が認められます。
災害義援金などが代表的です。
●② 特定公益増進法人(学校法人、認定NPO法人など)への寄付金
「損金算入限度額」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択可能です。
認定NPO法人への寄付金は、中小企業でも利用されるケースが増えています。
●③ 一般寄付金(上記に該当しないもの)
損金算入限度額が設定されており、全額を経費にすることはできません。
協賛金や地域イベント支援が該当しますが、広告宣伝としての性質があれば「広告宣伝費」として扱える場合もあります。
▼寄付金の限度額は、次の2要素で計算
資本金等の額
所得金額(当期利益)
限度額計算は複雑なため、実務では慎重な判断が求められます。
3.実務上の判断軸:迷いやすいポイント
寄付金を扱う際には、以下の点で判断が必要になります。
●① 寄付先がどの区分か
認定NPOか一般NPOかで扱いが大きく異なります。
名称が似ていても税務区分が異なるケースがあるため要確認です。
●② 寄付の「目的」と「対価性」
・広告枠を与えられる
・ホームページに企業名が掲載される
など、対価性が認められれば寄付金ではなく「広告宣伝費」として扱える場合があります。
●③ 契約書・領収書・決議書の有無
税務調査では、合理的な支出であることを示す「証拠」が求められます。
●④ 税額控除を使うか、損金算入を選ぶか
金額・利益状況により有利不利が変わるため、ケースごとに比較検討が必要です。
4.よくある誤解と修正
寄付金には、実務でよく見られる間違いがあります。
❌ 誤解①:寄付金は“全額経費”になる
→ 一般寄付金は限度額があり、超過部分は経費にできません。
❌ 誤解②:NPOに寄付すれば税額控除が使える
→ 「認定NPO」である必要があります。一般NPOは対象外です。
❌ 誤解③:協賛金はすべて寄付金扱い
→ 対価性(広告の提供)があれば「広告宣伝費」として損金算入可能。
誤解のまま処理すると、否認・追徴課税・加算税のリスクにつながります。
5.現場で役立つチェックポイント
寄付金の取り扱いで迷わないために、次の項目を確認することをおすすめします。
▼寄付を検討する前に確認すること
寄付先の法人格・区分(認定NPOかどうか)
支出目的(寄付か広告宣伝か)
寄付金の限度額に余裕があるか
税額控除との比較検討
▼寄付をした後に必ず行うこと
領収書・契約書・振込記録の保管
社内決裁の書面化(取締役会議事録など)
会計処理の区分(寄付金/広告宣伝費)の明確化
これらの手順を整えることで、節税効果と税務の安全性を両立できます。
6.まとめ・行動のすすめ
寄付金は、社会に貢献しながら企業の価値を高める重要な取組です。
しかし税務の世界では、寄付先・金額・目的によって取り扱いが大きく異なるため、正確な制度理解が欠かせません。
「この寄付は経費にできるのか?」
「税額控除を使えるのか?」
こうした疑問が生じた際は、早めに専門家へ相談することで、税務リスクを抑えつつ最適な選択ができます。
寄付についてのご不明点や、制度適用の可否判断などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の意思決定をサポートし、最善の処理方法をご提案いたします。
【在庫管理が節税につながる理由】 —在庫の“見える化”が企業財務を強くする—
1.導入:なぜ「在庫管理」に税務上の注目が集まるのか
在庫は、業種を問わず多くの企業にとって「売上の源泉」である一方、適切な管理がされていなければ“税務リスクの温床”にもなり得ます。
特に中小企業では、棚卸の手順が曖昧だったり、在庫評価が担当者任せになり、結果として決算に影響してしまうケースが少なくありません。
在庫は「資産」であり、期末在庫が多いと利益が増え、逆に少ないと利益が減ります。だからこそ、在庫管理は経営管理であると同時に、正確な税務申告に直結する重要テーマといえます。
本稿では、在庫管理がどのように節税につながるのか、その仕組みと判断軸を、2025年時点の税法に基づき整理します。
2.制度解説:在庫評価と利益の関係
税務上の「在庫(棚卸資産)」は、取得価額または低価法が原則です(法人税法第22条・同施行令)。
期末在庫が増えると、その分だけ当期の売上原価が減り、結果として利益が増えます。逆に、在庫が減ると利益は減ります。
▼売上原価の計算式
つまり、期末在庫を正しく評価できるかどうかが、利益と納税額に直結します。
特に、劣化・破損・陳腐化(型落ち品)などで価値が下がった在庫は、税務上「評価損」を計上できる場合があります。これが節税につながる大きなポイントです。
3.実務上の判断軸:担当者が迷いやすいポイント
在庫管理で判断が難しいのは、次のようなケースです。
●①「本当に使えない在庫」かどうか
劣化や破損があっても、証拠(写真・廃棄記録・棚卸表)がないと評価損は認められない可能性があります。
●②「陳腐化(型落ち)」の判断基準
家電、アパレル、季節商品などは、販売価値が大幅に下がることがあります。
ただし、値下げ販売の事実や市況下落の証拠が必要です。
●③棚卸の方法
・実地棚卸をしていない
・担当者ごとに評価基準が異なる
・棚卸差異の原因を追跡していない
——これらは税務調査で特にチェックされるポイントです。
●④「仕掛品・原材料」などの評価
製造業では、仕掛品や加工途中の材料の評価が複雑になりやすく、算定方法に一貫性が必要です。
4.よくある誤解と、そのリスク
在庫管理には、次のような誤解が多く見られます。
❌ 誤解①:在庫は“実地棚卸”をしなくても推定でよい
→ 税務上は、実地棚卸が原則。推定は原則認められません。
推定で算定すると、後日否認され、追徴課税につながる恐れがあります。
❌ 誤解②:使えなくなった在庫は捨てれば経費になる
→ 廃棄の事実と理由を示す証拠が必要。
特に、大量廃棄の場合は廃棄記録や写真が求められます。
❌ 誤解③:古くなったものは一律に評価損にできる
→ 実際の販売価格の下落、型落ちの事実など、合理的な根拠が必須です。
誤った判断は税務調査での否認につながり、追加の納税や加算税のリスクが生じます。
5.現場で役立つ対策・チェックポイント
在庫管理を節税につなげるには、「正しい評価」と「証拠の残し方」が重要です。
▼年度末前に確認しておくべきポイント
棚卸の実施日と手順を明確化する(マニュアル化)
劣化・破損・陳腐化在庫の洗い出し
廃棄記録の保存(写真・数量・廃棄理由)
市場価格の下落があれば、**価格証明(値下げ履歴や競合価格)**を保管
仕掛品・原材料の評価基準を一貫して運用する
棚卸差異が出た場合は、原因を把握し、次回の管理改善につなげる
▼在庫管理の整備は、次の経営効果も生みます
資金繰りの改善(不要在庫の圧縮)
発注ミスの削減
粗利率の改善
不正・ロスの防止
経営判断のスピード向上
税務だけでなく、経営管理全体に好循環をもたらす“投資対効果の高い取り組み”といえます。
6.まとめ・行動のすすめ
在庫管理は「節税テクニック」のように語られることがありますが、本質は“正しく企業活動を記録する”という基本にあります。
適切な棚卸と評価は、税務リスクを下げるだけでなく、経営の透明性を高め、企業の信頼性向上にもつながります。
「期末が近づいたから棚卸をする」のではなく、平時からの在庫管理の整備が、最も確実で持続的な節税につながる方法です。
在庫管理や在庫評価の見直しをご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の業種・在庫特性に応じて、最適な方法を丁寧にご提案いたします。
年末賞与で「節税効果を最大化」する方法 ― 2025年の税務と実務のポイント ―
1.導入:年末賞与が注目される理由
年末は、1年の業績を踏まえて社員への「賞与(ボーナス)」を支給する企業が多い時期です。
賞与は社員のモチベーションを高める重要な手段である一方、法人にとっては「損金算入できる時期」や「支給方法」によって、節税効果に大きな差が生じます。
特に、支給時期の判断を誤ると、損金算入の時期が翌期にずれ込み、税負担が重くなるケースも見られます。
本稿では、制度上の正確な理解とともに、「年末賞与をどう扱えば節税効果を最大化できるか」を、実務的な視点で整理します。
2.制度解説:賞与の損金算入と源泉徴収の基本
法人税法上、賞与は「実際に支給した事業年度」に損金算入できます(法人税法22条、法人税基本通達9-2-41)。
したがって、決算期末までに支給が完了していることが前提条件です。
たとえば12月決算の会社であれば、12月末までに賞与を支給(または確定)する必要があります。
また、賞与を支給する際には以下の手続きが必要です。
| 手続項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 支給時に天引き | 翌月10日までに納付 |
| 社会保険料 | 賞与支給届を提出 | 健康保険・厚生年金の標準賞与額で計算 |
| 雇用保険料 | 同様に控除・納付 | 上限は年間150万円まで反映 |
3.実務上の判断軸:損金算入の“タイミング”と“確定要件”
節税効果を最大化するには、「いつ損金にできるか」の判断が肝心です。
法人税法では、賞与を損金算入するために次の3要件を満たす必要があります(法人税法施行令72条の2)。
支給額が事業年度末までに全従業員に対して通知されている
事業年度末までに金額が確定している
事業年度終了後1か月以内に実際に支給されている
このいわゆる「未払賞与の損金算入要件」を満たせば、実際の支払いが翌月でも、当期の損金とすることが可能です。
ただし、1人でも支給額が未確定の従業員がいれば、全体が損金算入できなくなるため、注意が必要です。
4.よくある誤解と修正
誤解①:「賞与を計上すれば自動的に損金算入できる」
→ 実際には「確定通知+支給期日1か月以内」の要件が必要。未払計上だけでは認められません。誤解②:「取締役賞与も経費にできる」
→ 役員への賞与は「定期同額給与」または「事前確定届出給与」でなければ損金不算入となります(法人税法34条)。役員賞与は別のルールで管理すべきです。誤解③:「支給額を一律カットすれば節税になる」
→ 賞与額の減額は従業員の士気低下や離職につながり、結果的に経営コスト増を招くこともあります。単純なコスト削減は得策ではありません。
5.現場で役立つ実務チェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| ✅ 支給総額の決定 | 役員会・取締役会で議事録を残しておく |
| ✅ 従業員ごとの支給額通知 | 書面・メールなどで本人に確定通知を行う |
| ✅ 支給日程 | 期末から1か月以内に実際の支給 |
| ✅ 社会保険・源泉税の処理 | 各届出・納付期限をスケジュールに反映 |
| ✅ 役員分との区分 | 従業員賞与と明確に区別し、別管理 |
実務のポイント
・支給日と経理処理日を明確にし、会計システム上でも同一期間に反映させる
・税務調査では「通知の証拠書類(社内メール・Excel一覧・回覧文書)」の提示が求められるケースが多い
6.まとめ:適切な賞与運用が“信頼経営”につながる
賞与は「感謝と評価の象徴」であると同時に、税務・会計上の精緻な判断が求められる取引です。
法令要件を正確に押さえ、タイミングを誤らずに処理することで、節税効果を最大化できるだけでなく、従業員への誠実な姿勢としても評価されます。
藁総合会計事務所では、年末賞与の計算・支給時期の判断・損金算入可否の確認など、実務全般をサポートしております。
「節税」と「信頼」の両立を目指す経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【注意喚起】賃上げ促進税制の「補填額」に要注意― 名称だけで判断せず、交付要件で確認を ―
1. 結論
賃上げ促進税制の計算において、給与等の支給額から控除すべき「補填額」は、交付要件等で「給与負担の軽減目的」と明示されている補助金・助成金に限られます。
一方で、名称に「賃上げ」「処遇改善」「人材育成」などの文言が含まれていても、目的が異なれば補填額に該当しない場合があります。
したがって、補助金・助成金の名称だけで判断せず、交付要綱・支給決定通知書の内容確認が極めて重要です。
2. 背景と法的根拠
賃上げ促進税制(租税特別措置法第42条の12の5等)では、雇用者給与等支給額を算定する際、
「国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等のうち、給与等の支給額の負担を軽減する目的で支給されるものの金額」
を控除する(=補填額として除く)と定められています(措法42の12の5第6項、同施行令29の7)。
しかし「補填額」に該当するかどうかの判断は、補助金の交付目的・交付要件によって個別に異なります。
3. 名称だけで判断できない理由
(1)「賃上げ」や「処遇改善」と書かれていても目的が異なることがある
例えば、
- 看護職員処遇改善評価料
- 介護職員処遇改善加算
- 社会保険適用時処遇改善コース(キャリアアップ助成金)
これらはいずれも「賃上げ」「処遇改善」と名がつきますが、**医療・介護報酬や保険料制度に基づく対価(役務提供の報酬)**であるため、補填額には含まれません。
(2)逆に、名称に「賃上げ」が含まれなくても補填額になるものもある
たとえば、
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- 人材開発支援助成金(訓練中賃金助成)
- 特定求職者雇用開発助成金
などは、賃金負担を直接支援する仕組みであり、交付要綱に「賃金負担軽減」や「賃金助成」の趣旨が明記されているため、補填額に該当します。
4. 実務での確認ポイント
補助金・助成金を受け取った場合には、以下の3点を確認することが重要です。
| チェック項目 | 内容 | 実務対応 |
|---|---|---|
| ① 交付要綱の目的欄 | 「賃金」「給与」「人件費」「雇用主負担軽減」などの文言があるか | 記載があれば補填額の可能性が高い |
| ② 支給対象経費欄 | 「賃金助成」「給与補助」など具体的に給与支給額を対象としているか | 対象なら補填額の可能性あり |
| ③ 支給決定通知書 | 「交付目的」や「助成対象事業」が明記されているか | 不明な場合は要照会・要メモ |
5. 税務上の留意点
- 補填額は「受領した日の属する事業年度」の給与等支給額から控除します。
- 令和6年度以降は、役務の提供対価(医療・介護報酬など)を補填額に含めないとする取扱いが明確化されています。
- 交付要綱の目的が複合的な場合(例:設備投資+賃金支援)、按分処理が求められることもあります。
6. よくある誤認パターン
| 誤認例 | 正しい考え方 |
|---|---|
| 「業務改善助成金」は設備投資だから補填額にならない | 実際は最低賃金引上げとセットで賃金支援を行う制度。交付要件に「賃金引上げ」があり、補填額となる可能性がある。 |
| 「処遇改善加算」も給与アップのための支給だから補填額だ | 実際はサービス提供の対価として受け取る報酬。補填額には含まれない。 |
| 「キャリアアップ助成金」はすべて補填額になる | 社会保険適用時処遇改善コースなど一部は補填額に含めない扱い。コースごとに要確認。 |
7. まとめと実務アクション
- 補助金・助成金を受給したら、必ず交付要綱・通知書を確認する。
- 「賃金負担軽減」「給与補助」等の記載があれば、補填額の可能性あり。
- 不明な場合は、補助金事務局または税務署に事前照会を行う。
- 税務申告時には、補填額の控除根拠を**文書で保存(交付要綱・通知書コピー添付)**する。
8. 参考リンク(確認日:2025年10月17日)
- 国税庁「賃上げ促進税制の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927.htm - 中小企業庁「賃上げ促進税制ガイドブック(令和6年度版)」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf - 厚生労働省「賃上げ支援助成金パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html - 国税庁「法人税基本通達(措法42の12の5関係)」改正(令和6年度)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/241025/pdf/r.pdf
事前確定届出給与について
事前確定届出給与とは、役員に支給する給与の金額や支給時期を事前に確定し、税務署に届け出る制度です。これを利用するためには、株主総会決議から1ヶ月以内、または事業年度開始から4ヶ月以内の早い時期に税務署へ届出が必要です。この制度は、役員に支払う給与やボーナスを損金算入するために重要です。届出た内容(支給額や支給時期)を守らない場合、その給与は損金に算入されません。
事前確定届出給与のポイントは以下の通りです:
- 届出期限:事前確定届出給与を採用するには、税務署に対して株主総会で決定された役員報酬の金額や支給時期を事業年度開始から4ヶ月以内、もしくは株主総会決議から1ヶ月以内のいずれか早い方で届け出る必要があります。この期限を守らなければ、報酬が損金として認められなくなるリスクが高まります。
- 届出の内容:事前に届け出た給与額や支給時期は厳守する必要があります。税務署への届出と異なる金額や時期で給与が支払われた場合、税務上その部分の給与は損金算入が認められない可能性があり、法人税の負担が増えることになります。このため、届出後の管理は非常に重要です。
- 変更不可:原則として、届出後に給与の金額や支給時期を変更することはできません。例外的な状況(例えば、役員の職務変更や会社の経営状況の大幅な変化など)がある場合を除き、届出時の計画をそのまま実行しなければなりません。
- 書類の整備:事前確定届出給与を申請する際には、株主総会や取締役会の議事録など、報酬の決定が適切に行われたことを証明するための書類を整備し、これを税務署に提出する必要があります。これらの書類は税務調査などで確認される可能性があるため、確実に保管しておくことが求められます。
- 事前確定届出給与の目的:事前確定届出給与は、役員に支払われる給与やボーナスを計画的に損金として処理することを目的としています。法人税法上、役員に対する支払いは厳密なルールが定められており、これに違反すると損金不算入のリスクが生じます。そのため、企業は適切な手続きを踏み、役員報酬を税務上有利に取り扱うためにこの制度を活用します。
事前確定届け出給与のまとめ
事前確定届出給与は、上記の内容になりますが、顧問税理士としてはあまりやりたくありません。
事前届出による制度であり、届け出た内容と異なる役員報酬を支払うと、ペナルティが大きいからです。
法人税法上損金の額に算入することができなうえ、所得税は役員報酬として課税されることになります。
社会保険料の負担を下げたいと相談がありますが、危ういです。
役員報酬の改定について(経営状況の著しい悪化)
役員報酬
役員報酬とは、企業の取締役や監査役などの役員に対して支払われる報酬を指します。役員報酬には、給与、ボーナス、ストックオプション、退職金などが含まれ、税法上の取り扱いとして、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の3つに分類されます。
中小企業における役員報酬の取り扱いで知っておくべきことは、定期同額給与と事前確定届出給与となります。
定期同額給与の改定
定期同額給与とは、法人税法上、役員に毎月同じ金額を支給する給与のことを指します。
この給与は、事業年度の途中で変更することができず、決められた期間中は一律の金額で支給される必要があります。
改定の時期は、事業年度開始日から3ヶ月以内であれば、理由を問わず変更可能です。
定時の改定以外には、役員の職務内容の変更や経営状況の悪化など、特定の理由が必要です。
経営状況の悪化について
「経営状況の悪化」とは、企業の収益性や財務状況が著しく低下することを指します。この悪化の理由には、売上の急減、取引先の倒産、自然災害、技術革新による市場環境の変化などがあります。これにより、企業は負債が増加し、資金繰りに困難を抱えるようになり、事業の継続が危ぶまれる事態に至ることもあります。
特に定期同額給与の改定において「経営状況の著しい悪化」が認められる条件は、通常の経営活動では対応できないような予測外の状況が発生した場合を指します。たとえば、リーマンショックやパンデミックのような経済的危機、あるいは主要取引先の突然の倒産などが該当します。
このような悪化は、会社のキャッシュフローに大きな影響を与え、社員や役員への給与支払いに支障が出る場合もあります。そのため、役員報酬の減額や見直しを行うことが、企業の存続のためにやむを得ない選択肢となります。経営状況の悪化による給与の改定は、国税庁のガイドラインに基づき厳密に判断されるため、適切な書類の提出や証拠の提示が求められます。
国税庁のガイドラインとしては、役員給与に関するQ&Aを参考にしてください。
ただ、このガイドラインは絶対ではありません。企業の様々な事案毎に、個別具体的な事情があり、国税局不服審判所や裁判所の判例が積み重ねられる必要があるものです。
令和5年審査請求の概要の公表 | 税務・会計の専門家 藁総合会計事務所
審査請求は、納税者が税務署長や国税局長の処分に不服がある場合に、国税不服審判所に取消しや変更を求める制度です。
処分をした税務署長や国税局長ではなく、国税不服審判所が公正な第三者の立場で、納税者の正当な権利利益の救済を図ることを目的となっています。
令和5年度には3,917件の審査請求がありました。
理岩5年の審査請求の処理件数は2,873件で、認容割合は9.7%で、納税者にとっては厳しい判断をくだされています。
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の一部地域における終了について
日税連を通じて国税庁から、石川県及び富山県を対象に国税に関する法律に基づく申告、納付等の期限の延長措置について、指定地域の内一部を除き、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告、納付等の期限を令和6年7月31日とする旨周知依頼がありました。
詳しくは、次のURLをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm
試験研究費の税額控除制度はどんな試験研究をすれば使える?
試験研究費の税額控除制度というものがあります。試験研究費の額に応じて、一定の割合で計算した金額を法人税額から控除することができる制度です。法人税の節税でよく出てくる減価償却費の特別償却などの制度は毎年計上する経費を前倒しで計上し、前倒しで計上した年度の法人税額を減らすことになりますが、償却額は全体では増える訳ではないので、前倒しで計上した翌年度からは計上額が増えてしまいます。一方でこの試験研究費の税額控除制度は、法人税額から特別に税額を控除するので、この制度を適用しても翌年からの税額が影響するわけでもありませんし、適用できるのであれば絶対に適用したい制度です。試験研究費の額の十二%を法人税額から控除できます。(上限の規定はあり。)しかし、試験研究というと、大企業で、研究所があって、新たな技術を研究して、発明する・・・というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。そのため、自分の会社には関係無いなと思っているかもしれません。では、実際にはどのようなものが「試験研究費」としてこの制度の対象となるのでしょうか。
【試験研究費の額】
この制度の対象となる試験研究費の額は次の通りです。
1 製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るためまたは利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限ります。)のために要する費用。
2 新たな役務の開発に係る試験研究(新サービス研究)として①大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部、主要な部分が自動化されている機器または技術を用いて行われる情報の収集。②その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウエアを用いて行われる分析。③その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計④その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであることおよびその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であるとみとめられるものであることの確認。
どうでしょうか?自社で該当しそうなものはありましたでしょうか?ここで言う「新たな」とは、「今まで世の中になかった」という意味ではなく、「その企業にとっての新たなサービス」という意味です。また、以前から提供しているサービスに関連する試験研究であっても、新たな内容が付加される場合やサービスの提供方法が新しくなる場合などは「新たな」サービスに該当します。何か発明しないといけないと言うものではないのです。また、これらの試験研究は自社で行うのではなく、他者に委託して行ったものも対象です。
【経済産業省のQ&Aから】
Q 顧客のインターネットアクセスを自動で解析し、顧客に最適な商品提案を行うためのソフトウェアを開発していますが、税制の対象になりますか?
A 独自にアルゴリズムの開発を行い、これを特定のソフトウエアとして実装すれば製品の開発に係る試験研究となり得ます。また、同種のソフトウェアを開発し、自社内プロセスにおいて実装した場合は、技術の改良に係る試験研究となり得ます。
Q 情報の収集について、他者からデータを購⼊した場合には情報の収集になるのでしょうか?
A 当該データが、「⼤量の情報を収集する機能を有し、その全部⼜は主要な部分が⾃動化されている機器⼜は技術」によって収集されたものであれば、情報の収集に該当します。
Q 情報の収集や分析のプロセスについては、⾃社内で⾏うのではなく、外部に委託しようと考えていますが、その場合も対象になるのでしょうか?
A サービス設計⼯程の全てを実⾏することの判定については、法⼈がその全部⼜は⼀部を委託により⾏うかどうかは問わないこととなりますので、外部に委託した部分があった場合も対象になります。
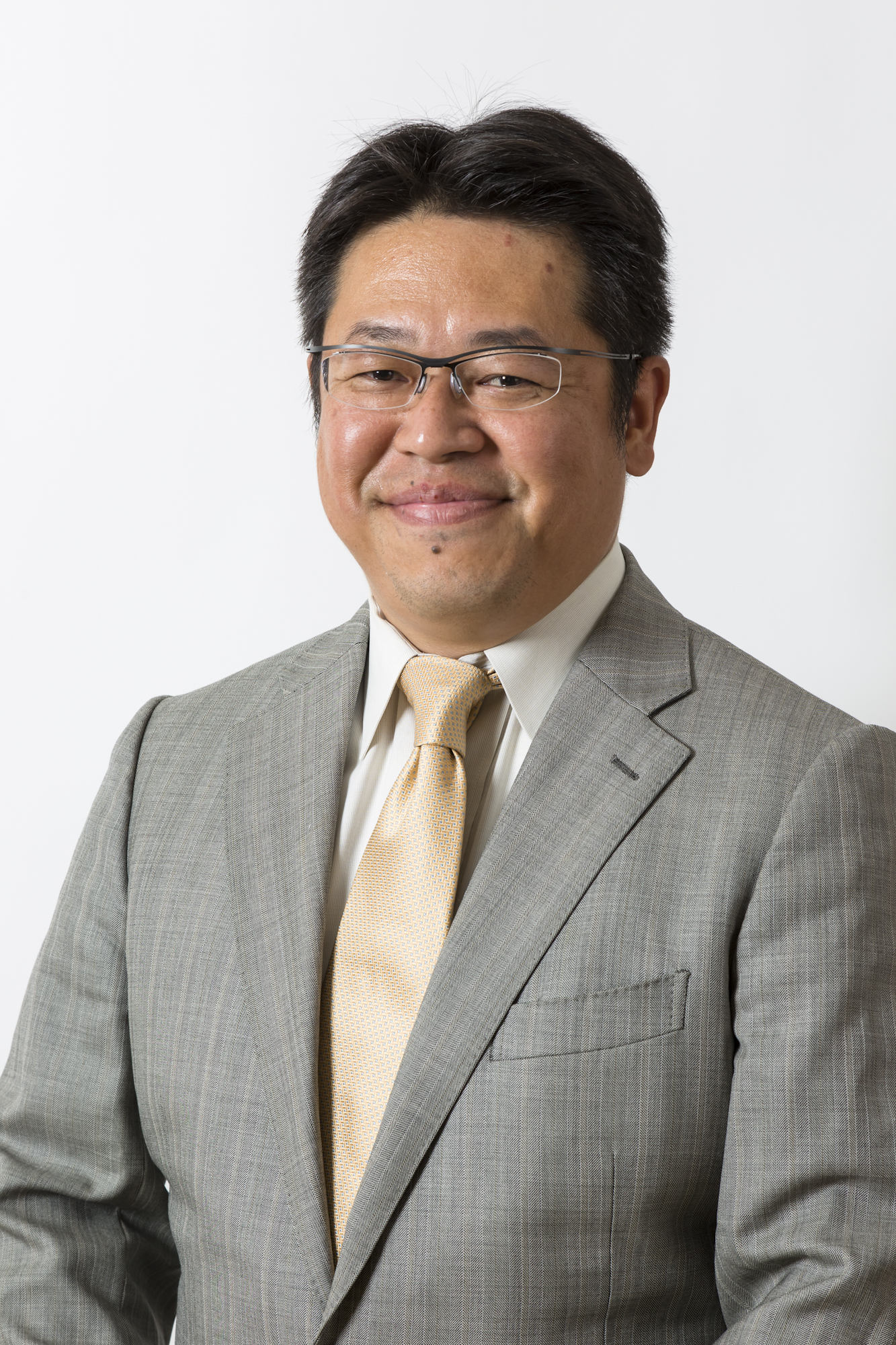 税理士 藁信博(
税理士 藁信博(