経営者が忘れがちな「個人側の税金」とは ― 会社の数字だけ見ていると、思わぬ落とし穴があります ―
法人経営者の方とお話をしていると、
「会社の税金は税理士に任せているから大丈夫」
「法人税・消費税は把握している」
という声をよく耳にします。
一方で、意外と見落とされやすいのが、
経営者“個人”として負担している税金です。
会社の数字がきれいに整理されていても、
個人側の税金を正しく理解していないと、
「手取りが思ったより増えない」
「あとから想定外の税負担が出てくる」
といった事態が起こりがちです。
今回は、**経営者が特に忘れやすい「個人側の税金」**について、実務の視点から整理します。
1.「会社」と「個人」は税金の世界では別人格
まず大前提として、
会社(法人)と経営者個人は、税務上まったく別の存在です。
法人 → 法人税・法人住民税・法人事業税・消費税
個人 → 所得税・住民税・社会保険料 など
この切り分けを意識していないと、
「会社で利益が出ている=自分も余裕がある」
と誤解してしまいがちです。
実際には、
会社の利益と、経営者個人の可処分所得は一致しません。
2.経営者が忘れがちな個人側の税金①
役員報酬にかかる「所得税・住民税」
経営者個人にとって、最も基本となるのが役員報酬です。
役員報酬は、
法人側では「損金(経費)」になりますが
個人側では「給与所得」として課税されます。
その結果、
所得税(累進税率)
住民税(一律10%)
が毎月・毎年、確実にかかります。
法人税だけを意識して役員報酬を高く設定すると、
個人側の税率が一気に上がり、トータルでは不利になるケースも少なくありません。
3.経営者が忘れがちな個人側の税金②
住民税は「ワンテンポ遅れて」やってくる
住民税は、前年の所得をもとに課税されます。
そのため、
会社の業績が落ちた
役員報酬を下げた
という年でも、
前年の好調時の所得に基づく住民税が課税されることがあります。
「今年は報酬を下げたのに、住民税が高い」
と感じる理由の多くは、このタイムラグです。
資金繰りや生活費を考えるうえで、
住民税は必ず“翌年分まで含めて”見積もる必要があります。
4.経営者が忘れがちな個人側の税金③
社会保険料は「税金ではないが、実質的な負担」
厳密には税金ではありませんが、
**社会保険料(健康保険・厚生年金)**は、
経営者個人にとって非常に大きな負担です。
特に注意が必要なのは、
役員報酬を上げる
→ 社会保険料も連動して増える
→ 手取りは思ったほど増えない
という構造です。
法人・個人トータルで見ると、
「税金より社会保険料の方が重い」
というケースも珍しくありません。
5.経営者が忘れがちな個人側の税金④
配当・不動産・副収入への課税
経営者の方は、以下のような収入をお持ちのことも多いです。
株式の配当
不動産収入
副業・講演料・原稿料 など
これらは、役員報酬とは別に
個人の所得として確定申告が必要になります。
特に注意したいのは、
「会社とは関係ない収入だから大丈夫」
「源泉徴収されているから問題ない」
と思い込んでしまうケースです。
実際には、
合算すると税率が変わる、住民税が増える
といった影響が出ることがあります。
6.なぜ「個人側の税金」は見落とされやすいのか
理由はシンプルです。
法人税・消費税 → 決算で“見える”
個人の税金 → 給与天引きや翌年課税で“見えにくい”
その結果、
会社の数字だけを見て経営判断をしてしまう
ということが起こります。
しかし、本来重要なのは
「法人+個人トータルで、どれだけ残るか」
という視点です。
7.まとめ:経営者こそ「個人側」まで含めて考える
経営者にとっての税務は、
「会社の税金」だけでは完結しません。
役員報酬
所得税・住民税
社会保険料
副収入への課税
これらを含めて初めて、
本当の意味での手取り・可処分所得が見えてきます。
役員報酬の金額や設計一つで、
将来の税負担や生活の安定性は大きく変わります。
「会社の税金は見ているけれど、
個人側までは整理できていない」
そう感じた方は、
ぜひ一度、法人と個人をセットで見直してみてください。
状況に応じた最適なバランスについて、
お気軽にご相談ください。
年末こそ“帳簿のメンテナンス”を
1. はじめに ― 年末は「帳簿の大掃除」のベストタイミング
12月は、会計上も税務上も「区切りの時期」です。
日々の忙しさで後回しになっていた帳簿や書類が、気がつけば積み上がっている…そんな声をよく聞きます。
しかし、年末に帳簿を整えておくことで、
決算の精度が上がり、税金リスクも減り、翌年のスタートを軽くする
という、大きなメリットがあります。
今日は、実務で押さえておきたい“帳簿メンテナンスのポイント”を整理します。
2. このタイミングで見直したい「5つの帳簿」
① 売掛金・買掛金の未収・未払の漏れチェック
・請求書の出し忘れ
・相手からの請求書未着
・入金済みだが入金処理が未記帳
こうしたズレは決算数値を歪めます。
得意先・仕入先ごとに突合して、漏れを確実に洗い出しましょう。
② 立替金・仮払金・預り金の“残高放置”は危険
仮払金・立替金は“残高が動かない勘定科目”として、税務調査で必ず確認されます。
・担当者が退職した
・処理し忘れた
・領収書がどこかにあるはず
こうした曖昧な残高は放置しないことが重要です。
③ 固定資産の棚卸・除却忘れの確認
実態として使用していない資産を除却せず、
帳簿上だけ“存在し続けている”ケースが非常に多く見られます。
・壊れて捨てた
・入れ替えたのに古い資産が残っている
・中古で売却したのに処理していない
固定資産は年度末だけでなく、年末の時点でも棚卸をしておくと誤差が減ります。
④ 現金・小口現金の突合
小口現金はズレが起こりやすい科目です。
特に、誰が管理しているのか不明確な場合はリスクが高いです。
この時期に残高を突き合わせ、“宙に浮いた現金”をゼロにしましょう。
⑤ 経費の計上漏れ ― 特に「12月に発生したが請求は1月」の費用
・広告費
・通信費
・外注費
・社会保険料
など、12月分の費用が翌月請求になるものは、計上漏れが起こりやすいポイントです。
3. 帳簿のメンテナンスで得られる3つのメリット
① 決算がスムーズに進む
年明けの処理が軽くなり、決算スケジュールが短縮できます。
② 税務リスクが下がる
仮払金・未払金の放置は“調査で疑われるポイント”です。
年末に整理することで、余計な指摘を避けられます。
③ 経営判断の精度が上がる
正しい数値は、経営の羅針盤です。
「年末の棚卸」の積み重ねが、翌年の意思決定を確実なものにします。
4. まとめ ― 年末は「帳簿の健康診断」を
帳簿のメンテナンスは、華やかな業務ではありませんが、
最も効果が出る“地味だけど効く”管理業務です。
今の忙しさを少しだけ止めて、
12月に帳簿を整える時間を取ってみてください。
きっと、翌年の経営と経理が「格段にラクになる」ことを実感していただけると思います。
【2023〜2025年の労働時間制度の変更点】 ― 割増率・上限規制・運用強化を一枚で理解する ―
2023年から2025年にかけて、労働時間や残業の扱いに関する重要な制度変更が段階的に行われています。
特に中小企業は、「いつ・何が変わったのか」「自社が対象なのか」が分かりにくく、誤解しやすい領域です。
本稿では、“割増率”と“残業時間の上限規制”を分けて理解できるように再編成し、経営者・実務担当者が押さえるべきポイントを整理しました。
■ 1.まず押さえるべき全体像
労働時間まわりの制度変更は、大きく3つに分類できます。
① 割増賃金率の変更(給与計算に関係)
② 残業時間の上限規制(働かせ方に関係)
③ 運用ルールの厳格化(管理職・裁量労働制など)
それぞれの発生時期がズレているため、混乱が生じやすくなっています。
■ 2.【割増率】が変わったのは“2023年のみ”
◎ 2023年4月:月60時間超の残業は「割増率50%」が中小企業にも適用
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 中小企業すべて |
| 改正内容 | 月60時間超の時間外労働 → 割増50% |
| 従来 | 大企業のみ50%、中小企業は25%だった |
| 影響 | 給与計算・36協定・固定残業制度の見直し |
▶ 「割増率の適用範囲の拡大」は2023年が唯一の該当。
▶ 2024年・2025年には“割増率の追加変更”はありません。
■ 3.【上限規制】の適用は“2024年から本格化”
2024年から、これまで猶予されていた業種にも「残業時間の上限規制」が適用されました。
これは“割増率”とはまったく別の制度です。
◎ 2024年4月:特定業種に上限規制が適用
| 対象業種 | 主な内容 |
|---|---|
| 建設業 | 年720時間が上限(例外の厳格化) |
| 運送業(自動車運転業務) | 年960時間まで |
| 医師 | 健康確保措置の義務化 |
▶ 「働かせ方」そのものを制限する内容で、割増率とは別物。
▶ 36協定、シフト、休憩・休日管理の見直しが必要。
■ 4.【2025年】は“割増率ではなく運用の厳格化”
2025年に「割増率が上がる」などの法改正はありません。
しかし、実務レベルでは以下の“運用強化”が明確に進みます。
◎ 2025年の重要ポイント(新制度ではなく、適用運用の強化)
管理監督者の基準の厳格判断(名ばかり管理職の否定)
深夜・休日労働の区分管理の明確化
労働時間の電子管理(PCログ、ICカード等)の適正利用
副業・兼業者の労働時間通算ルールの整備
裁量労働制の適正運用チェック
特別条項付き36協定の「実態確認」強化
▶ 制度そのものではなく“適用の実務が厳しくなる”年と理解するのが正確。
■ 5.経営者が押さえるべき実務ポイント(2025年対応)
【1】給与計算の確認(割増率50%対応は済んでいるか)
月60時間超の残業は正しく50%計算されているか
固定残業代と実残業時間の整合性が取れているか
【2】働き方の見直し(上限規制対応)
業種特有の上限に該当しないか
36協定の内容が実態と一致しているか
【3】管理職の扱い(最重要)
管理監督者の基準判定に問題がないか
裁量労働制の文書・協議の整備
【4】労働時間の電子記録の扱い
PCログ/勤怠記録のどちらを正とするかルール化
労働時間の二重管理の危険がないか
■ 6.まとめ
「割増率が変わった」のは2023年のみ。
「上限規制」は2024年から本格適用。
「2025年」は制度変更というより“運用が厳しくなる年”。
制度の理解が曖昧なまま放置すると、給与計算の誤り、固定残業代の無効化、名ばかり管理職の指摘など、会社にとって大きなリスクにつながります。
会社の状況に合わせて、労務・税務・人事の観点から総合的な見直しを行うことが重要です。
【AI時代をどう歩くか】 ― 税理士としてChatGPTと向き合い、活用し続けている理由 ―
はじめに:静かな変化の真っただ中で
ChatGPTが登場してから、世の中は急速に変わり始めました。
ただ、変化というものは外から見ると“突然の大波”のように見えますが、
実際はとても静かに、少しずつ、しかし確実に進んでいくものです。
私自身、AIが騒がれ始めた頃は、
「税理士業務にどこまで役に立つのだろう?」
「制度改正や判例のような専門領域に対応できるのか?」
と半信半疑でした。
ところが、使い始めて2年半。
今では次のように考えています。
“AIは、税理士がより税理士らしくあるための道具である。”
社会貢献で節税も?寄付金の扱いと注意点― 制度の正確な理解が、適切な経費化と税務リスク回避につながる ―
1.導入:社会貢献への関心の高まりと“寄付金”の落とし穴
近年、企業による社会貢献活動が注目され、NPOへの寄付や災害支援、地域活動への協賛など、寄付金を支出する機会が増えています。
しかし一方で、「良いことをしたから経費になるはず」「寄付金は全部落とせる」といった誤解も少なくありません。
寄付金には、法人税法上の厳密な区分があり、その扱いに誤りがあると、税務調査で否認される可能性があります。
適切な判断のためには制度の理解が不可欠です。本稿では、寄付金の種類・限度額・注意点を整理し、実務で迷わないための基礎知識を解説します。
2.制度解説:寄付金の基礎と法人税法上のルール
(※2025年時点の法令に基づく)
法人税法では寄付金を次の3区分に分類しています。
●① 国や地方公共団体への寄付金
全額損金算入が認められます。
災害義援金などが代表的です。
●② 特定公益増進法人(学校法人、認定NPO法人など)への寄付金
「損金算入限度額」と「税額控除」のどちらか有利な方を選択可能です。
認定NPO法人への寄付金は、中小企業でも利用されるケースが増えています。
●③ 一般寄付金(上記に該当しないもの)
損金算入限度額が設定されており、全額を経費にすることはできません。
協賛金や地域イベント支援が該当しますが、広告宣伝としての性質があれば「広告宣伝費」として扱える場合もあります。
▼寄付金の限度額は、次の2要素で計算
資本金等の額
所得金額(当期利益)
限度額計算は複雑なため、実務では慎重な判断が求められます。
3.実務上の判断軸:迷いやすいポイント
寄付金を扱う際には、以下の点で判断が必要になります。
●① 寄付先がどの区分か
認定NPOか一般NPOかで扱いが大きく異なります。
名称が似ていても税務区分が異なるケースがあるため要確認です。
●② 寄付の「目的」と「対価性」
・広告枠を与えられる
・ホームページに企業名が掲載される
など、対価性が認められれば寄付金ではなく「広告宣伝費」として扱える場合があります。
●③ 契約書・領収書・決議書の有無
税務調査では、合理的な支出であることを示す「証拠」が求められます。
●④ 税額控除を使うか、損金算入を選ぶか
金額・利益状況により有利不利が変わるため、ケースごとに比較検討が必要です。
4.よくある誤解と修正
寄付金には、実務でよく見られる間違いがあります。
❌ 誤解①:寄付金は“全額経費”になる
→ 一般寄付金は限度額があり、超過部分は経費にできません。
❌ 誤解②:NPOに寄付すれば税額控除が使える
→ 「認定NPO」である必要があります。一般NPOは対象外です。
❌ 誤解③:協賛金はすべて寄付金扱い
→ 対価性(広告の提供)があれば「広告宣伝費」として損金算入可能。
誤解のまま処理すると、否認・追徴課税・加算税のリスクにつながります。
5.現場で役立つチェックポイント
寄付金の取り扱いで迷わないために、次の項目を確認することをおすすめします。
▼寄付を検討する前に確認すること
寄付先の法人格・区分(認定NPOかどうか)
支出目的(寄付か広告宣伝か)
寄付金の限度額に余裕があるか
税額控除との比較検討
▼寄付をした後に必ず行うこと
領収書・契約書・振込記録の保管
社内決裁の書面化(取締役会議事録など)
会計処理の区分(寄付金/広告宣伝費)の明確化
これらの手順を整えることで、節税効果と税務の安全性を両立できます。
6.まとめ・行動のすすめ
寄付金は、社会に貢献しながら企業の価値を高める重要な取組です。
しかし税務の世界では、寄付先・金額・目的によって取り扱いが大きく異なるため、正確な制度理解が欠かせません。
「この寄付は経費にできるのか?」
「税額控除を使えるのか?」
こうした疑問が生じた際は、早めに専門家へ相談することで、税務リスクを抑えつつ最適な選択ができます。
寄付についてのご不明点や、制度適用の可否判断などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の意思決定をサポートし、最善の処理方法をご提案いたします。
【在庫管理が節税につながる理由】 —在庫の“見える化”が企業財務を強くする—
1.導入:なぜ「在庫管理」に税務上の注目が集まるのか
在庫は、業種を問わず多くの企業にとって「売上の源泉」である一方、適切な管理がされていなければ“税務リスクの温床”にもなり得ます。
特に中小企業では、棚卸の手順が曖昧だったり、在庫評価が担当者任せになり、結果として決算に影響してしまうケースが少なくありません。
在庫は「資産」であり、期末在庫が多いと利益が増え、逆に少ないと利益が減ります。だからこそ、在庫管理は経営管理であると同時に、正確な税務申告に直結する重要テーマといえます。
本稿では、在庫管理がどのように節税につながるのか、その仕組みと判断軸を、2025年時点の税法に基づき整理します。
2.制度解説:在庫評価と利益の関係
税務上の「在庫(棚卸資産)」は、取得価額または低価法が原則です(法人税法第22条・同施行令)。
期末在庫が増えると、その分だけ当期の売上原価が減り、結果として利益が増えます。逆に、在庫が減ると利益は減ります。
▼売上原価の計算式
つまり、期末在庫を正しく評価できるかどうかが、利益と納税額に直結します。
特に、劣化・破損・陳腐化(型落ち品)などで価値が下がった在庫は、税務上「評価損」を計上できる場合があります。これが節税につながる大きなポイントです。
3.実務上の判断軸:担当者が迷いやすいポイント
在庫管理で判断が難しいのは、次のようなケースです。
●①「本当に使えない在庫」かどうか
劣化や破損があっても、証拠(写真・廃棄記録・棚卸表)がないと評価損は認められない可能性があります。
●②「陳腐化(型落ち)」の判断基準
家電、アパレル、季節商品などは、販売価値が大幅に下がることがあります。
ただし、値下げ販売の事実や市況下落の証拠が必要です。
●③棚卸の方法
・実地棚卸をしていない
・担当者ごとに評価基準が異なる
・棚卸差異の原因を追跡していない
——これらは税務調査で特にチェックされるポイントです。
●④「仕掛品・原材料」などの評価
製造業では、仕掛品や加工途中の材料の評価が複雑になりやすく、算定方法に一貫性が必要です。
4.よくある誤解と、そのリスク
在庫管理には、次のような誤解が多く見られます。
❌ 誤解①:在庫は“実地棚卸”をしなくても推定でよい
→ 税務上は、実地棚卸が原則。推定は原則認められません。
推定で算定すると、後日否認され、追徴課税につながる恐れがあります。
❌ 誤解②:使えなくなった在庫は捨てれば経費になる
→ 廃棄の事実と理由を示す証拠が必要。
特に、大量廃棄の場合は廃棄記録や写真が求められます。
❌ 誤解③:古くなったものは一律に評価損にできる
→ 実際の販売価格の下落、型落ちの事実など、合理的な根拠が必須です。
誤った判断は税務調査での否認につながり、追加の納税や加算税のリスクが生じます。
5.現場で役立つ対策・チェックポイント
在庫管理を節税につなげるには、「正しい評価」と「証拠の残し方」が重要です。
▼年度末前に確認しておくべきポイント
棚卸の実施日と手順を明確化する(マニュアル化)
劣化・破損・陳腐化在庫の洗い出し
廃棄記録の保存(写真・数量・廃棄理由)
市場価格の下落があれば、**価格証明(値下げ履歴や競合価格)**を保管
仕掛品・原材料の評価基準を一貫して運用する
棚卸差異が出た場合は、原因を把握し、次回の管理改善につなげる
▼在庫管理の整備は、次の経営効果も生みます
資金繰りの改善(不要在庫の圧縮)
発注ミスの削減
粗利率の改善
不正・ロスの防止
経営判断のスピード向上
税務だけでなく、経営管理全体に好循環をもたらす“投資対効果の高い取り組み”といえます。
6.まとめ・行動のすすめ
在庫管理は「節税テクニック」のように語られることがありますが、本質は“正しく企業活動を記録する”という基本にあります。
適切な棚卸と評価は、税務リスクを下げるだけでなく、経営の透明性を高め、企業の信頼性向上にもつながります。
「期末が近づいたから棚卸をする」のではなく、平時からの在庫管理の整備が、最も確実で持続的な節税につながる方法です。
在庫管理や在庫評価の見直しをご検討中の方は、どうぞお気軽にご相談ください。
御社の業種・在庫特性に応じて、最適な方法を丁寧にご提案いたします。
年末賞与で「節税効果を最大化」する方法 ― 2025年の税務と実務のポイント ―
1.導入:年末賞与が注目される理由
年末は、1年の業績を踏まえて社員への「賞与(ボーナス)」を支給する企業が多い時期です。
賞与は社員のモチベーションを高める重要な手段である一方、法人にとっては「損金算入できる時期」や「支給方法」によって、節税効果に大きな差が生じます。
特に、支給時期の判断を誤ると、損金算入の時期が翌期にずれ込み、税負担が重くなるケースも見られます。
本稿では、制度上の正確な理解とともに、「年末賞与をどう扱えば節税効果を最大化できるか」を、実務的な視点で整理します。
2.制度解説:賞与の損金算入と源泉徴収の基本
法人税法上、賞与は「実際に支給した事業年度」に損金算入できます(法人税法22条、法人税基本通達9-2-41)。
したがって、決算期末までに支給が完了していることが前提条件です。
たとえば12月決算の会社であれば、12月末までに賞与を支給(または確定)する必要があります。
また、賞与を支給する際には以下の手続きが必要です。
| 手続項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 源泉所得税 | 支給時に天引き | 翌月10日までに納付 |
| 社会保険料 | 賞与支給届を提出 | 健康保険・厚生年金の標準賞与額で計算 |
| 雇用保険料 | 同様に控除・納付 | 上限は年間150万円まで反映 |
3.実務上の判断軸:損金算入の“タイミング”と“確定要件”
節税効果を最大化するには、「いつ損金にできるか」の判断が肝心です。
法人税法では、賞与を損金算入するために次の3要件を満たす必要があります(法人税法施行令72条の2)。
支給額が事業年度末までに全従業員に対して通知されている
事業年度末までに金額が確定している
事業年度終了後1か月以内に実際に支給されている
このいわゆる「未払賞与の損金算入要件」を満たせば、実際の支払いが翌月でも、当期の損金とすることが可能です。
ただし、1人でも支給額が未確定の従業員がいれば、全体が損金算入できなくなるため、注意が必要です。
4.よくある誤解と修正
誤解①:「賞与を計上すれば自動的に損金算入できる」
→ 実際には「確定通知+支給期日1か月以内」の要件が必要。未払計上だけでは認められません。誤解②:「取締役賞与も経費にできる」
→ 役員への賞与は「定期同額給与」または「事前確定届出給与」でなければ損金不算入となります(法人税法34条)。役員賞与は別のルールで管理すべきです。誤解③:「支給額を一律カットすれば節税になる」
→ 賞与額の減額は従業員の士気低下や離職につながり、結果的に経営コスト増を招くこともあります。単純なコスト削減は得策ではありません。
5.現場で役立つ実務チェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| ✅ 支給総額の決定 | 役員会・取締役会で議事録を残しておく |
| ✅ 従業員ごとの支給額通知 | 書面・メールなどで本人に確定通知を行う |
| ✅ 支給日程 | 期末から1か月以内に実際の支給 |
| ✅ 社会保険・源泉税の処理 | 各届出・納付期限をスケジュールに反映 |
| ✅ 役員分との区分 | 従業員賞与と明確に区別し、別管理 |
実務のポイント
・支給日と経理処理日を明確にし、会計システム上でも同一期間に反映させる
・税務調査では「通知の証拠書類(社内メール・Excel一覧・回覧文書)」の提示が求められるケースが多い
6.まとめ:適切な賞与運用が“信頼経営”につながる
賞与は「感謝と評価の象徴」であると同時に、税務・会計上の精緻な判断が求められる取引です。
法令要件を正確に押さえ、タイミングを誤らずに処理することで、節税効果を最大化できるだけでなく、従業員への誠実な姿勢としても評価されます。
藁総合会計事務所では、年末賞与の計算・支給時期の判断・損金算入可否の確認など、実務全般をサポートしております。
「節税」と「信頼」の両立を目指す経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【令和7年分】確定申告の準備のお願い
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
さて、今年も残すところわずかとなりました。
当事務所では、令和7年分(2025年分)の所得税確定申告に向けた準備資料を、令和7年11月10日(月)に「確定申告準備書面」とともにメール便で発送いたします。
お手元に届きましたら、内容をご確認のうえ、必要資料のご準備をお願いいたします。
Ⅰ.年内にやらなければならないこと
所得税は 1月1日~12月31日 の1年間の所得を基に計算します。
年内の行動が来年の税金額を大きく左右しますので、早めのご対応をお願いいたします。
① 株式・投資信託の取引がある方へ
令和6年から新しいNISA制度が始まりました。
旧NISAや特定口座との損益通算ができません。
含み損のある株式の**「損出し」**など、年内売却による節税をご検討ください。
② 不動産の修繕を検討している方へ
修繕費は年内引き渡しで経費算入が可能です。
ただし、契約書・見積書の内容により資本的支出と判断される場合もあります。
年内に工事内容を確定させましょう。
③ 設備投資・パソコンの買換えを検討している方へ
「中小企業投資促進税制」などにより、一定の設備は年内取得で即時償却や税額控除の対象になります。
青色申告の方は年内購入がおすすめです。
④ 減価償却方法を見直したい方へ
定額法・定率法の変更には届出が必要です。
翌期から変更を希望する場合は、12月31日までにご連絡ください。
⑤ 回収不能な売掛金・貸付金がある場合
法的手続きや取引停止など、貸倒損失の要件を満たすかを確認し、年内に処理を検討しましょう。
⑥ 生前贈与をお考えの方へ
令和6年から「相続時精算課税制度」に年間110万円の基礎控除が導入されました。
暦年贈与との比較検討のうえ、年内に贈与契約書を作成して実行することをおすすめします。
Ⅱ.医療費控除について
同封の「医療費の集計表」をご利用ください。
受診者・医療機関ごとに集計し、ご提出をお願いいたします。
領収書の提出は不要ですが、当事務所で集計をご希望の場合は領収書をご送付ください。
(別途料金が発生します)
Ⅲ.ふるさと納税・寄附金控除について
ワンストップ特例を利用された方が確定申告を行うと、特例は無効となります。
確定申告を行う場合は、全ての寄附金受領証明書またはマイナポータル連携データをご準備ください。
Ⅳ.インボイス制度について
令和5年10月に開始されたインボイス制度は、令和7年で3年目を迎えます。
登録事業者の方は、**登録番号(T+13桁)**の記載をお忘れなく。
登録取消を希望する場合の届出期限:令和7年12月17日(水)
免税事業者が令和7年から課税事業者となる場合の届出期限:令和7年12月31日(水)
令和8年9月30日まで、「2割特例」(小規模事業者向け負担軽減措置)が利用可能です。
Ⅴ.提出期限のご案内
確定申告に必要な書類一式は、令和7年1月30日(金)まで にご提出ください。
提出が遅れますと、申告期限(3月17日予定)に間に合わない場合があります。
お早めのご準備をお願いいたします。
Ⅵ.ご相談のお願い
次のようなご相談は年内にご連絡ください。
相続税・贈与税の試算
設備投資の時期・内容
減価償却方法の変更
課税方式・届出の検討
節税シミュレーション
おわりに
「確定申告準備書面」は、令和7年11月11日(月)にメール便でお届けいたします。
お手元に届きましたら内容をご確認のうえ、必要資料をご準備ください。
確定申告準備書類および関連資料は、令和8(2026)年1月31日までにご送付くださいますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。
📞 お問い合わせ先
藁総合会計事務所
〒142-0041 東京都品川区戸越2-5-3ウェルマン戸越3階
TEL:03-5749-4568 | E-mail:info@warara.com
営業時間:平日9:00~18:00(土日祝休)
外国人不動産売却が進む日本で注意すべき「非居住者への源泉徴収義務」
1. 日本経済と外国人投資家の動向
近年、日本では外国人労働者や外国人経営者を取り巻く制度が厳格化する傾向にあります。
在留資格の取得・更新要件も見直され、「外国人を取り巻く環境が右傾化している」と指摘されることも少なくありません。
一方で、日本経済は労働力・投資資金の両面で外国人の貢献に依存しています。
もし、こうした外国人投資家や経営者が日本市場から撤退(エスケープ)する動きが広がれば、不動産市場にも波及し、外国人所有の不動産売却が相次ぐ可能性もあります。
このとき、日本人が非居住者(外国人)から不動産を購入する場合に発生する税務リスクとして、
特に重要なのが「源泉徴収義務」です。
2. 非居住者への不動産代金支払いには「源泉徴収」が必要
結論
非居住者(または外国法人)から日本国内の不動産を購入する場合、
買主(日本居住者・法人)には、譲渡代金の10.21%を源泉徴収して国に納付する義務があります。
🔹 税率:10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)
🔹 対象:土地・建物等の譲渡代金
🔹 納付期限:支払日の翌月10日まで
計算例
売買価格が1億円の場合:
源泉徴収額=1億円 × 10.21% = 1,021万円
売主への支払額=8,979万円
買主は1,021万円を税務署に納付
3. 法的根拠と参考資料
| 区分 | 出典 | 内容 |
|---|---|---|
| 所得税法第212条第1項第5号 | 非居住者への不動産譲渡代金の支払に関する源泉徴収義務 | |
| 所得税法施行令第322条 | 「国内にある資産の譲渡」定義 | |
| 所得税基本通達212-1 | 国内不動産の範囲の明示 | |
| 国税庁タックスアンサー No.12036 | 非居住者からの不動産購入時の源泉徴収義務の説明(確認日:2025年11月7日) |
4. 実務対応の流れ
売主の居住区分を確認
在留資格・住民票の有無・帰国状況などから「非居住者」かを判定。支払時に源泉徴収
売買契約額に10.21%を乗じて差し引く。翌月10日までに納付
「所得税徴収高計算書」により所轄税務署へ納付。支払調書の提出
翌年1月末までに「不動産等の譲渡の対価の支払調書」を提出。源泉徴収票を売主に交付
非居住者側はこれを基に確定申告し、過剰分を還付申請可能。
5. 注意点とリスク
居住者・非居住者の判定は支払時点で行う。
売主が法人(外国法人)の場合も源泉徴収対象。
不動産業者を介しても、最終支払者が個人なら義務あり。
源泉徴収を怠ると、買主側に不納付加算税・延滞税が課される。
源泉徴収は譲渡所得税の前払いであり、最終的な税額とは異なる。
6. 今後の展望と専門家の役割
外国人投資家が日本不動産市場から撤退する場合、
短期的には不動産価格の調整局面が生じる可能性もあります。
ただし、手続の煩雑さや税務リスクが壁となり、
買い手側の負担が増すことにも注意が必要です。
税理士や不動産業者は、
「非居住者との取引における源泉徴収義務」を確実に把握し、
契約書面や資金決済の段階で誤りがないようサポートすることが求められます。
7. まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 非居住者・外国法人への不動産代金支払 |
| 税率 | 10.21%(所得税+復興特別税) |
| 納付期限 | 支払月の翌月10日まで |
| 書類 | 所得税徴収高計算書、支払調書、源泉徴収票 |
| リスク | 源泉徴収漏れ=買主にペナルティ |
8. 専門家からのアドバイス
契約締結前に「売主が非居住者かどうか」を必ず確認
契約書に「源泉徴収条項」を明記
税務署への納付は期限厳守(遅延時は罰則)
外国人売主側には還付請求の案内も行う
✅ まとめると…
外国人不動産投資家の動向が変化する今こそ、
「非居住者への源泉徴収義務」を正確に理解し、
税務リスクを未然に防ぐことが、買主・仲介業者双方に求められています。
「今年のうちにやるべきこと」5選 ― 年末を迎える前に確認したい、税務・労務・経営のチェックポイント ―
1.導入:年末を迎える前に確認すべき「経営の足元」
11月以降、決算や年末調整、社会保険料の見直しなど、経理・労務担当者にとって慌ただしい時期がやってきます。
「あとでまとめて処理しよう」と後回しにした結果、年明けに慌てて修正や追加対応に追われるケースも少なくありません。
本稿では、2025年のうちに確認・実行しておきたい重要項目5選を、税務・会計・労務の観点から整理します。
2.制度解説:年末対応が重要となる背景
法人・個人を問わず、12月は「期中調整」「法定期限前の行為」「来期への布石」が重なる時期です。
税務署や年金事務所の手続きも年明けに集中するため、年内に判断・届出を済ませることが、円滑な経営管理につながります。
また、2025年は以下のような制度改正・トレンドにも留意が必要です。
インボイス制度の猶予期間が終了し、経過措置が段階的に縮小
電子帳簿保存法の「宥恕期間」終了に伴う実務対応の厳格化
賃上げ促進税制の適用拡大(中小企業向け要件変更)
社会保険の適用拡大(パート・アルバイトを含む)
各種補助金・助成金の予算切り替え期
3.実務上の判断軸:「今年のうちにやるべきこと」5選
(1)交際費・福利厚生費の整理
年末に駆け込みで支出が増える時期です。交際費・会議費・福利厚生費の区分が曖昧なまま処理すると、税務調査で損金算入が否認されるリスクがあります。
社員向け→福利厚生費
取引先向け→交際費
社内会議・打合せ→会議費(合理的な説明要)
ポイント: 支出目的・参加者・内容をメモ等で残すことで、経費性の説明が容易になります。
(2)固定資産の棚卸・償却費の確認
使用していない備品や資産を放置していると、会計上も税務上も不適切です。
廃棄・除却を決定した資産は年内に除却処理
少額減価償却資産(30万円未満)の特例は年内購入分まで
例外: 中小企業者等特例の適用対象は資本金1億円以下の法人などに限定されます。
(3)役員給与・賞与の見直し
役員報酬は「定期同額給与」または「事前確定届出給与」として事前に決めた金額しか損金算入できません。
賞与を支給予定の場合は、**事前確定届出書の提出期限(支給日1か月前)**を必ず確認しましょう。
(4)年末調整と社会保険の適用確認
パート・アルバイトの週20時間以上勤務者について、2025年10月からの適用拡大を見据え、年内に勤務実態を点検しておくと安心です。
また、年末調整では以下の点を確認しましょう。
控除証明書(生命保険・地震保険など)の提出漏れ
住宅ローン控除の初年度書類
扶養親族の所得確認
(5)電子帳簿保存法・インボイス対応の最終確認
電子取引データ(PDF請求書など)は電子保存が原則義務化されています。
やむを得ず紙で保存している場合は、**保存要件(タイムスタンプ・訂正履歴・検索性)**を満たすか確認しましょう。
インボイス登録番号の記載漏れも、控除否認のリスク要因です。
4.よくある誤解と修正
| よくある誤解 | 実際の取扱い |
|---|---|
| 「12月に払えば全部当期経費になる」 | 役員給与や前払費用は、支出時期よりも契約・届出の内容が優先されます。 |
| 「交際費は年間800万円まで損金」 | 資本金1億円超の法人は除外。対象範囲や超過分の扱いに注意。 |
| 「電子帳簿保存はまだ猶予中」 | 宥恕期間は終了。実務上は即時対応が求められます。 |
5.現場で役立つ実務チェックリスト
固定資産台帳の更新・除却確認
年末調整資料の回収状況
電子帳簿保存法対応(社内ルール・システム)
役員賞与届出書の提出期限確認
交際費・福利厚生費の区分明確化
6.まとめ:早めの準備が信頼経営につながる
年末対応は「後でまとめて」ではなく、「今のうちに一点ずつ確認する」ことが肝要です。
税務リスクを防ぐだけでなく、決算書の信頼性や金融機関からの評価向上にもつながります。
藁総合会計事務所では、年末調整・インボイス・電子帳簿保存法への実務対応についてもサポートしています。
経営者の皆さまが安心して新年を迎えられるよう、ぜひお気軽にご相談ください。
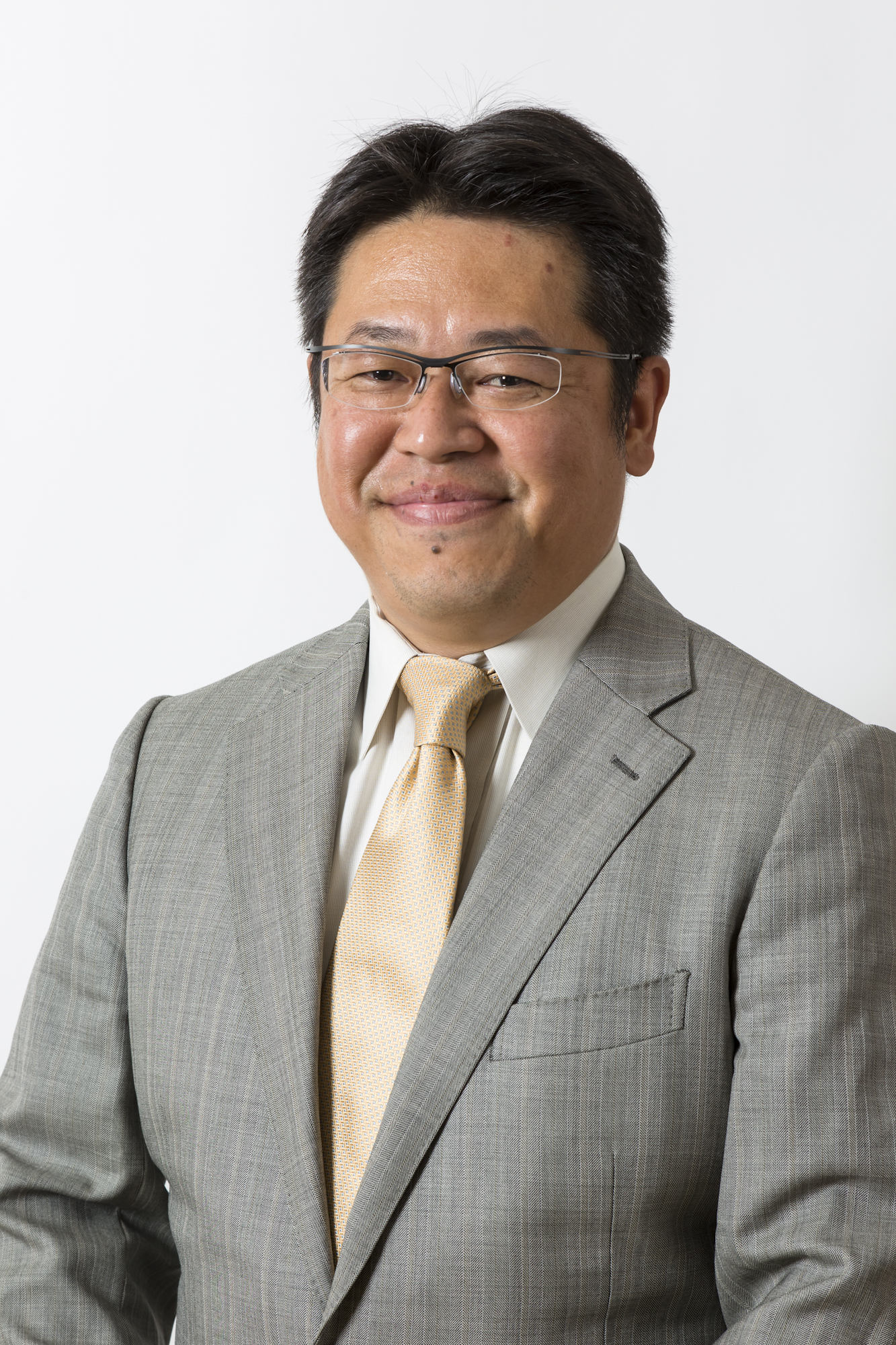 税理士 藁信博(
税理士 藁信博(